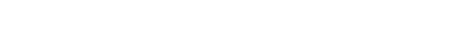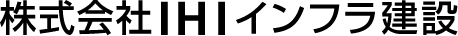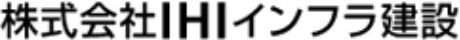My Job / My Story大変だけどオモシロイ、
水門設計の世界とは?
- 設計
- 防災・⽔⾨
K.R2021年入社


My Jobどんなシゴトをしていますか?
ダムや河川にある水門の設計を担当しています。
「水門」をパッとイメージできない人は、ダムを想像すると分かりやすいかもしれません。ダムは川の水位を調整するために放流を行いますが、その際に鋼製の扉を開閉して放流量を調節します。この鋼製の扉こそが自分が設計を担当する水門設備です。日本中のダムや河川などに設置されている大中小さまざまな水門設備により水を適切にコントロールすることで、周辺地域の暮らしを豊かにし守っています。水門設備は、扉体と呼ばれる鋼製の扉、開閉装置と呼ばれる歯車などで構成された機械装置、それらの動作を制御する操作制御設備で構成されており、その中でも主に扉体と開閉装置の設計を担当しています。現代では過去に多く作られてきた水門設備の老朽化が課題の一つで、自分は現在修繕工事の設計担当としてさまざまな年代に作られた水門設備に携わっています。
私の原点と入社の理由My Story
「単純」って言われても、
スケールのデカい
モノづくりがしたかった。

「いかにも技術者っぽいね」と言われるかもしれませんが、子どもの頃から何かを作ることが好きで、プラモデルやレゴブロックに熱中していました。でも、自分の進路を決定づけたのは、中学3年生の時の経験です。夜中まで受験勉強を頑張っていたある日、息抜きをしようとテレビをつけると、画面に映し出されたのはロボットコンテストの様子。自分より年上と言っても、せいぜい2歳〜3歳ほどしか年の離れていない学生が、でっかいロボットを自在に動かしゲームに挑んでいる姿を見てグッときました。「自分もこんなモノづくりがしたい!」そう思って、中学卒業後の進路を工業高等専門学校にシフトチェンジ。ところが入学後はテニスに夢中になってしまって……。結局、ロボコンチームには参加しなかったけど、モノづくりを一生の仕事にしたいと思ったのはこの時期です。やがて就職の時期を迎えて思ったのは「どうせならスケールのデカいモノづくりがしたい」ということ。飛行機?自動車?それもいいけどもっとたくさんの人と関わって、大きなモノづくりに挑める仕事ってないかな?そんな目線で見つけたのがインフラ業界、橋やダムの水門を作るIHIインフラ建設という会社でした。単純ですけど『インフラ』という言葉から感じるスケール感や、たくさんの人の役に立つモノづくりであることに惹かれました。
私のシゴト体験談My Story
何十年も先の未来に、
自分の名前が設計者として残るって
すごくないですか?

インフラの世界に飛び込んだ先に待っていたのは、水門設備の設計という仕事です。実を言えば入社当初は『水門』と言われても上手くイメージできませんでした。でもこれが面白いんです!仕事の中で一番多いのが、過去に建設された水門設備の修繕工事。対峙するのは50年とか、70年前の技術者が作った巨大な構造物。例えば、北海道にある水門は横幅なんと40m!間近で見た時はデカさに圧倒されました。そうかと思えば別の現場で、高さ15mはあろうかという水門と出会ったときには、口を開けたまま見上げてしまいました。一方で、数メートル規模の小さな水門もあります。水門って同じものが一つもない。新たな水門に出会う度、そこに込められた技術に「すごい」と思うのですが、関心してばかりもいられません。なにしろ、今度はその継承した技術に自分が設計者として挑む必要があるからです。
何より重要なのは事前調査です。設計と言えども、現場に足を運んで何度も調査します。何十年も使われた水門であればあるほど、設計図は残っていても記録に記されていない当時の工夫された技術力が隠れていたりするからです。実物を自分の目で確認し、さらに情報を集めて修繕計画を考え、設計図に描き起こします。修繕箇所に対して適切な方法とは?今の基準に合致させるためにどんな工夫が必要?時には答えが見つからずに頭を抱えることもあります。正直に言えば大変です。でもこの仕事ならではのやりがいがあります。なにしろ自分が設計者として設計図に名を刻んだ水門が、この先何十年も残っていくわけです。もしかすると、未来の設計者が過去の担当として自分の名前を発見するかもしれません。過去から未来にバトンを受け渡しているようで、ロマンがあると思いませんか。
プロジェクトの一員として
チームで知識を出し合い臨んだ、あの日。

今までで一番印象に残っているのは、やっぱり入社2年目に担当した栃木県の河川の水門修繕プロジェクトです。当時はまだ経験が浅く、最初はプロジェクトチームの一員に加わっているだけでした。ところがしばらくするとそのチームの設計の主担当に任命されてしまいました。正直ビビりました。修繕対象の水門は50年も使われている土砂を吐き出すための設備で、その扉体の腐食が進み、水門設備としての機能が低下していました。再生のためには金属板を溶接して補強するしかありません。ただこれが難しい。腐食が広範囲すぎて溶接箇所をうまく特定できません。だから何度も現場に行き、状態をくまなく調べました。そして調査結果を会社に持ち帰りチームのメンバーと共有し、ダンボールで再現模型を作ったりして溶接箇所を明確にする日々が続きます。さらにその情報を持ってあらゆる人の意見を聞きました。この繰り返しの結果、ようやく設計が決まって工事がスタートした時は嬉しかったのですが、その後も次から次に問題が発覚します。その度に現場に直行して実物を確認し、現場関係者の意見を聞き、解決策を模索する日々が続きます。この時はさすがに挫けそうでした。
それでも先輩・上司からの良きアドバイスや、現場で作業に従事した方々の努力と工夫の結果、溶接による補強作業が終わります。最後に待っていたのは、関係者全員が固唾を飲んで見守りながらの“試運転”です。この時の緊張感は今までに味わったことのないものでした。「動かなかったらどうしよう」という不安が頭の中に浮かんでは消えていきますが、無事に稼働した瞬間は、心の底から安堵しました。この経験は今でも自分の土台になっています。多くの人と力を合わせて、人の役に立つモノづくりをすることがどれだけ大変で面白いか、この時初めて理解できたような気がします。
Next Interview1年で積み上げた設計図、
およそ700枚。
橋をつくるって、
こんなに大変だったのか。