技術と感性が呼応し,ともに羽ばたく
株式会社IHI
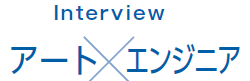
生と死,そのあいだにあるものを写真や彫刻などで問う現代美術作家の野村在さん.ロンドンで学び,ニューヨークをはじめ国内外で活躍する野村さんの,近年の作品の中でも特徴的なのが水中に故人のポートレートを印刷する《Fantôme(ファントーム)》.世界でも類を見ない作品を,IHIの技術者たちが試行錯誤を重ねながら完成へとサポートしました.アートとテクノロジーが出会い,技術と感性がともに羽ばたく“今”について,野村さんとエンジニアたちが語り合いました.

ものづくりの技術がアートの繊細さを実現する
― 野村さんの作品《 Fantôme 》は,ガラスの水槽の上にプリンターが搭載されたもの.このプリンターが動き出すと,水の中に人物写真が印刷され,ぼんやりと立ち現れます.その姿は水の中でたゆたい,一定の時間がたつとゆっくりと消えてまた透明な水へと戻る.印刷されるのはいずれも亡くなった人で,インターネットからの申し込みで,希望者が写真を送ると,希望の時間に印刷されるというインタラクティブな仕組みも備えています.この作品は2024 年3 ~ 4 月に東京の資生堂ギャラリーで展示され,2025 年夏には海外でのビエンナーレにも招かれています.作品の制作から設置,展示中の細かな調整や追加の仕様変更などに臨機応変に応え続けているのが,IHIのものづくりサークル(※1)から生まれたエンジニアチームです.まずは,このチームと野村さんの出会いから聞きました.

1979 年生まれ.2009 年ロンドン大学ゴールドスミス校・MFA 修了,2013 年に武蔵野美術大学博士課程を修了.主な展示に,「第17 回shiseido art egg 野村在展 」資生堂ギャラリー( 東京,2024 ),「OPEN SITE 8 」TOKAS 本郷( 東京,2024 ),「あいちトリエンナーレ」( 愛知,2016 ) など.
野村: IHIさんとは,2018 年ごろi-Base(イノベーション推進拠点であるIgnition Base,IHI横浜事業所内)の建設中に出会いがありまして,ここに作品を置かせていただくことになりました.その後,私の当時の国立(東京都)のアトリエにIHIの方々が来られたことがあって.水中に写真を印刷する装置の1 号機がすでにあったのですが,それを見て「これ,うちの技術でできるんじゃない」と言われて,ものづくりサークルを紹介していただいた,という流れです.
― IHIのエンジニアたちは,それぞれに専門性を持ち特定の分野のプロフェッショナルとして技術を日々高めています.一方で,製品の開発から運用までの全体を見渡すことを意識しつつも,実際の業務では専門領域に集中することが多く,全体を深く把握するのが難しい場面があるのが現状です.そこで,さまざまな職種や職歴を持つメンバーが集い,通常の業務にとらわれず,ものづくりに関するアイデアや技術を共有し,実践的な活動を行う社内部活としてのものづくりサークルがあるのですね?

新居: そうです.ものづくりサークルで「水中に写真を印刷する」と聞いたときは,どういうこと? と思いました.解像度良くきれいにできるの? とか.エンジニアとしてはきれいに見えなくちゃ意味がないと思っていましたから.それでも「やりたい人?」と募ったら,複数人が手を挙げてくれました.
野村: もっとも,プリンターではなく最初からもっと精巧に水の中に人の像を浮かび上がらせる装置を作るという考えもあったのですが,僕は写真を印刷するという行為にこだわった.紙が入ったら動き出すという誰もが知っているプリンターで水中に写真を印刷することが重要なんです.

野崎: 仕組みを簡単に説明します.プリンターだったら紙が流れるところを薄い水の膜が流れていて,そこにインクが出て写真を印刷します.このプリンター部分は既存のものを改良しました.紙の代わりとなる水膜にインクを乗せて流していくと,周りの水とちょっとずつ混ざりながら,水槽の下の方に引っ張られて出ていく.これも,水槽の中の水流がそのように動くように制御しています.するとぼんやりと写真が浮かび上がるのですが,インクは徐々に水中に拡散して,像は動き続けてやがて崩れて消えます
新居: 水流の実験は何度もやりましたね.プリンターのインクが一定時間は残って,きれいに拡散するにはどんな流れをつくったらいいのか,など.実は,流れもずっと動き続けているのではなく,3 秒動いたら3 秒止まるなど工夫を重ねています.
- 1ものづくりサークルとは,IHIのエンジニアたちが自主的に新しいアイデアを試し,技術を磨く場として設立されました.この活動を通じて,ものづくり精神を共有し,日常業務では得られない視点や発想力,展開力を育むことを目的としています.
「できません」とは悔しくて言えない
― 《 Fantôme 》は水中に写真を印刷する装置としては3 台目と聞いています.2 台目から改良されたのは主にどこですか?
野村: インターネットに接続して世界中の誰もが印刷できるようになった点と,インクを消す仕組みとしてオゾン水生成器を導入したことですね.実は,1 号機では水を浄化することを考えておらず,展示中にどんどん水が濁っていったんです.展示中にギャラリーの方から「水を換えて」と言われて換えたのですが,自分としてはけっこう痛みが残りました.人の想い,写真の人物の痕跡を捨ててしまうことですから.2 号機では,水をカーボンフィルターに通すことで再び透明にすることができたのですが,フィルターの数が膨大になり,しかも捨てられない.人の想いが詰まったものだから.今もニューヨークのアトリエにあります.
野崎: 僕たちは3 号機から関わることになったのですが,たぶん最初の打ち合わせで話したのが,どうやって水中のインクを取り除くかということ.今は異動してしまったメンバーが「オゾンが使えるのでは」と発案したのが始めでした.
野村: オゾンってすごいんですよね.分解する際に別の物質と結びつくことで水は透明になるのですが,実際にはインク粒子は残っていると聞いて感動しました.亡くなった方の「存在証明」というか.あと,オゾン層で知られているように,地球の自然界に存在する物質であることも良かった.
野崎: どこにオゾン水生成器をつけるかということを考えました.素早く水を透明にするのなら,水槽の下から泡を出せばいい.ただ,その消え方は在さんの感性とは合わず,結局水槽の上部にオゾンの泡の入った水の層をつくり,水流によってそれが動いて,水中に拡散したインクと触れて色が消えていくという方法になりました.
新居: 資生堂ギャラリーでの展示会の途中に在さんの要望で,オゾン水生成器をより大型のものに変えることになったんですよ.みんなで時間を忘れて作業しましたね.

大木: そうですね,普段の仕事だったら当初の仕様書どおりに作ります.でも,今回はいきなり大型装置に変えてパワーを上げようということに.とはいえ,在さんの求めるものを実現したくなるんですよ,僕らも.
野村: 大型の装置の購入は,さすがに,ひりつきました(笑).
大木: もうひとつ,3 号機では,インターネットを介して希望者が印刷を申し込めるようにしました.これも,制作の半ばで出てきたアイデアで.当初は「それは無理なんじゃないかな」と思ったんですよ.このような特殊な装置を動かすためには,マニュアルを作って講習をやって運用してもらうのが普通.ログに入れる情報と,印刷の希望時刻を入れて,写真を提出するという簡単なことでも,一般の方がこちらの仕様に合うように準備できるとは最初は思えなかったんです.でも,もちろんできた方がアートとしては面白い.そこで運用プログラムの方を変え,申し込みは一般的なGoogleのフォームやスプレッドシートを使うことで最終的には対応できるようにしました.
野村: 皆さん,ほんとすごい.僕が「5 年後には靴で空中を歩く作品を作りたい」と言ったら,この人たち「なんとかしましょう」とやっちゃうと思うんです.でも,新居さんには「在さん,大変なんですよ」と何度も怒られました.そこで実は,子供もやるような電子工学のキットを買って入門用のプログラムを書いて装置を動かすというのをやってみました.みんなに教えてもらいながら1 か月ぐらいかかった.それ以来,以前よりも感謝の気持ちが深まりました.
新居: こっちとしては,「できません」と言うのは悔しいじゃないですか.自分は,課題解決が好きで,技術でそれができるのは面白いんです.
大木: それと,今回は印刷する写真に関する情報をモニターで展示する部分も作りました.その情報の現れ方,フェードアウトの仕方も工夫しましたね.在さんからは細かい指定はなかったのですが,まず三つぐらいパターンを作って.かつ,後から変えたくなるだろうな,と思い対応できるようにしました.これは,長く一緒にやって分かってきたというのもあるのですが,在さんは,とても丁寧に筋道を立てて説明してくださるんです,コンセプトを.どんな思いで何を見せたいのか,何を実現したいのか.それがあるから,いきなり無理難題が降ってくるといいう感じではなく,「面白いもの,より良いものを作ろう」という気持ちになるし,できるところは,自分も工夫したくなります.
テクノロジーを介して人の感情,感性が刺激される
― エンジニアは,いわゆる“役立つ”ものや従来品よりも優れたものを作ることで,世の中に新しい価値を提供しています.一方で,アーティストは作品を通じて人々の心を動かし,感性を刺激し,社会に新たな視点や価値を提供する活動を行っています.アートは人生に,命の豊かさに,欠かせないものですが,エンジニアの皆さんはアート作品の制作に携わったことで,何を得ましたか?
野崎: 自分のアイデアが形になるというのもあるのですが,とにかく普段の仕事の枠とは違う枠で考えることかな,と思います.この先どんどん世の中は変わっていくし,どんな要求が出てくるか分からないじゃないですか.普段やっている仕事とは全く違う視点からのオーダーが来てそれに応えるというのは,考え方の幅を広げるという意味で新鮮です.思いがけないところに,この技術が適応できるかも,といった発想が広がります.
新居: エンジニアとして製品を開発し,お客さまにお届けした後は,実際にその製品が使用されている場面を直接目にする機会は少ないのが現状です.でも,アートは作ってギャラリーの真っ白い空間にポンと置かれて,そこで装置が稼働して作品として完成する.それを見て素直に美しいなと感動しました.空間全部が美しかったです.
大木: 確かにラボで作っていたものと同じとは思えませんでした.ライティングもきれいで神秘的で.見ているのも楽しかったです.
野村: 僕の作品って何が重要かと考えると,究極的には装置そのものではないのかもしれません.こういう装置を介して,何か人には見えていないものが可視化されたり,僕の感情が具現化されたり.そのトランジションを見ることは,すごくゾワゾワするし,たまらなく興味深いと思う.鑑賞者のコメントを聞いて,それをエンジニアのみんなとも共有できたというか,そうして作品が鑑賞者を含めみんなのものになったなぁと感じています.
新居: 無理難題があってもそれを自分たちの手で解決できたことは,エンジニアとして自信にもなりました.アート作品に携わることで,アーティストが思うことを具現化することにこだわりをある意味押し通すことも,新しいものを生むのには大切なんだなと気づきました.具体化するためのプロセスを体験できたことは,意味があると思います.
大木: 一般の方がインターネットで申し込むことを実現する過程や,この先海外での展示で,自分たち以外の人が調整したり運用したりするのを,日本からインターネットでサポートすることも実現しようとしていますが,これらは今取り組んでいるネットワークを介した業務の自動化に転用することにつながりそうです.
野村: 僕はずっと「人間とは何か」ということを考え続けているんです.そのミラーリングとしてテクノロジーを使う場合が多い.テクノロジーを使うのは人間で,人類の歴史上いつもいい方向にテクノロジーを使ってきたとは言い切れません.でも,それをアートにも使うことで,あらためて「人間とは」を問うことができると思っています.そういえば,この前ある講演会でお話したところ,それに来てくれたらしい全然知らない人が「IHIって会社は尊い」ってInstagramにあげていたんですよ.たぶん,後でIHIのことを検索して調べたんでしょうね.会社に対して「尊い」っていう表現(笑).そんなことが起こるのも,アートならではかなぁと思ったりしています.

Fantôme
